【ランスマの金哲彦コーチの最新刊!】
『正しいマラソン~どうすれば走り続けられるか? 』金哲彦・編著、山本正彦、河合美香、山下佐知子・共著 Vol.114
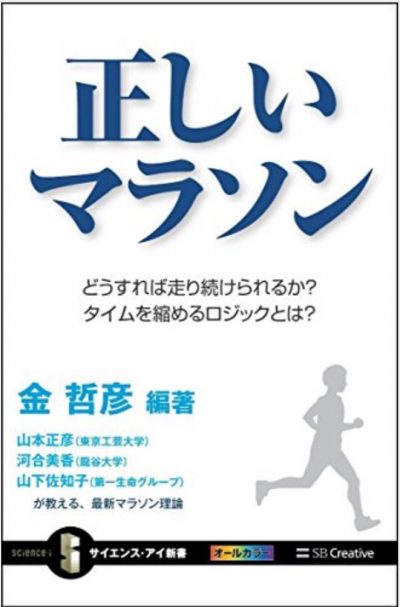
本日の一冊は、NHK BS1の市民ランナーを対象にした教養番組 「ラン×スマ」 でもよく知られている金哲彦コーチの最新刊。
ランニング本は出尽くした感がありますが、ジョギングやランニングにおけるケガや故障の話がいまだ取り沙汰される今日、走り方を見直すためにぜひ読んでいただきたく、ご紹介します。
金哲彦コーチは幾つものランニング本を出していますが、本書がほかと異なるのは、スポーツ栄養学や運動生理学の複数のスペシャリストと連携し、マラソン理論を解説している点です。
本書の中で「アメリカの『ランナーズワールド』誌に、ランナーたちがどのような接地をしているのかという記事がでていた。ヒールストライカー(かかと着地)が7割、ミッドフットストライカー(フラット着地)が2割、フォアフットストライカー(つま先よりの着地)が1割だそうである。」という話が出てきますが、着地は日ごろの姿勢に影響し、長時間スマホやパソコンを目にする現代人からすれば、ブレーキ気味の走りをしている人は9割以上ではないかと思います(もし否定される方がいらっしゃれば長期のケガなどの問題は少ないはずです)。大阪城公園や長居公園、淀川河川敷を走るランナーの着地を観察していると10人中9人、私のコーチング受講者の9割が身体の前方でのヒールストライカー(かかと着地)です。
ストライド走法、ヒールストライカー(かかと着地)の代表格であった野口みずき選手は慢性的な股関節痛に悩まされていたとも聞きます。ランニングでケガを少なくするためにはできるだけブレーキにならない着地をすることが重要です。
内容の大半は「基本」であり、これまでにランニング本を読み漁ってきたという読者には目新しい内容はありません。
走り出して1年以内の方や「ラン×スマ」 ファンの方が読めば、きっと得るところが多い一冊だと思います。
文庫サイズで通勤中の読書に最適です。ぜひチェックしてみてください。
▼本書より
歩きと走りの違い。歩くときには、必ず足裏のどこかが地面に接しているのに対し、走るときには、必ず足裏のどこかが地面に接しているのに対し、走るときには、どこも地面に接することなく宙に浮いている時間が生じる。この滞空時間は、ゆっくり走るときは20~30%であるが、速く走るほど割合が増し、長時間になる。
歩くと体重の1~1.2倍程度の衝撃を受けるが、走るとジョギングで2~3倍、速く走るとそれ以上の衝撃が生じる。
一般のランナーは、身長の60~70%の歩幅で走ることが多いが、野口みずき選手は身長150cmに対してストライドが147.7cmといわれており、ほぼ身長の歩幅で走っていることになる。
1分間あたり瀬古選手が200~210歩、猫さんは230歩という、高速回転のピッチ走法である。
ストライド走法やピッチ走法、明らかな定義は存在しない。選手本人やまわりのイメージで〇○走法といっているのだ。
マラソンを走り切るのに、体重が60kgのランナーであれば2633kcalのエネルギーが必要になる。身体に蓄えられたグリコーゲンが1500kcal程度なので、どうしても1000kcal以上不足してしまう。それを補うのが、脂肪である。
記録を目指すランナーにとって、血液を鍛えることも重要なトレーニングの一つなのだ。
ほめられない腕振りといえば、嫌々をするように腕を横に振るスタイルである。推進力にとぼしく、スピードにのって走ることができない。横に腕を振る癖があるランナーは、ピンポン球をもって走ると矯正できる。
アメリカの『ランナーズワールド』誌に、ランナーたちがどのような接地をしているのかという記事がでていた。ヒールストライカー(かかと着地)が7割、ミッドフットストライカー(フラット着地)が2割、フォアフットストライカー(つま先よりの着地)が1割だそうである。
ストライドが広すぎるランナーは加速と原則の差が大きくなる。狭すぎるランナーは加速と原則の差は小さいものの、スピードに乗り切れない。
注意したいのは、脚の振り出しが小さいと、着地の際につま先が地面を蹴るように着地してしまい、「詰まったような着地」になることだ。
減速が小さく、できるだけブレーキにならない着地をするためには、振り出した脚を、自分の重心の真下に素早く引き込むことである。
長距離走はスタートからゴールまで、体重を運ぶ競技ともいえる。
宙に浮いているときには、重心が放射線を描いて着地に向かう。この放射線の高さや幅が大きくなると、上下動が大きい走りになる。その場合、前進するためにより多くのエネルギーが必要になり、効率が悪い。
上下動は10cm。上下動が小さいほうがエネルギーが少なくてすむ。
筋肉の疲労困憊時の急な運動停止は、異常な硬直を促してしまうという、身体の反応のひとつなのだ。これを防ぐには、ごくごく軽い負荷の「足踏み」でもいいので、筋肉を動かし続けることだ。
【ランスマの金哲彦コーチの最新刊!】
『正しいマラソン~どうすれば走り続けられるか? 』金哲彦・編著 Vol.114