【意識をしてはダメ?ランニング中の姿勢や腕振り】
『トップアスリートに伝授した怪我をしない体と心の使いかた』小田伸午・小山田良治・本屋敷俊介・共著 Vol.118
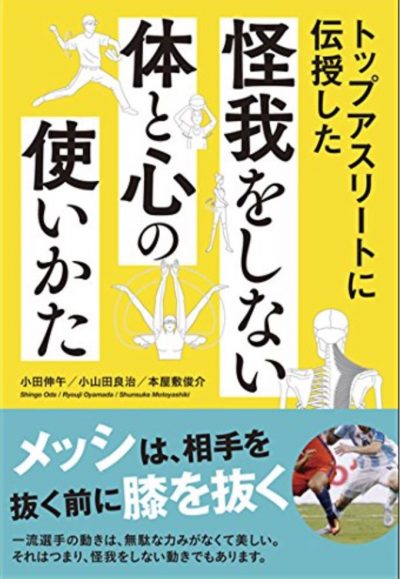
トレイルランナーズ大阪の安藤です。
書籍をご紹介する際は、私の考えとは関係なく「役立った」と思うものはすべてご紹介しています。ある時はAという考え方の書籍を紹介し、ある時はBという真逆の考え方の書籍を紹介する場合があり、すべては読者に自分で考えてもらうためです。よって「安藤さんが話していることと違いますね」「この著者は先日ご紹介されていた書籍と真逆のことを話していますね」ということも当然ながらありご了承ください。
本日の一冊は、『トップアスリートに伝授した怪我をしない体と心の使いかた』。
元日本代表ラグビーチームのトレーニングコーチで『アスリートの科学』など多数の著書を持つ小田伸午氏に小山田良治氏、プロ野球トレーナーの本屋敷俊介氏との共著。小山田氏は歩行と股関節の動きの研究家でもあり、本書でも起立の姿勢や歩行、股関節の使い方などが解説されており学びの大きい一冊になっています。
スポーツではケガを少なくして、量・質ともに高いトレーニングを続け、いかに結果につなげるかというのが重要です。
イチローにネイマールにメッシ、ドログバ、ウサイン・ボルトなど、スポーツ競技を限定せず優秀な選手の動きの分析が紹介されており、ランニングの姿勢や腕の振り、トレイルでの歩き方や走り方に繋がるヒントもあり、 大変興味深く読めました。
<肩凝りは胸凝りである>久しぶりに目から鱗が落ちる感じがしました。
個人的には、 <人間は、分析の結果として得た理想の動作を意識することによって、逆に動作は理想形から遠ざかるという仮説です>という冒頭文からちょっと考えさせられました。
わかりやすくランニングで例えれば著者は、<腕振りなどは意識をすることで肘や肩に力みが入る>というのです。スポーツ競技において確かに力みはマイナスに働きリラックスが重要ですが、私は「何の意識もなく練習するよりは意識することで動作が良くなる」と考えているからです。そこを力ませずに、別の運動動作を教えながら自然と体使いを身につけてもらうことがコーチの腕の見せどころのように思います。
ランニング本は溢れていますが、もっとこうした優秀な選手の動作を解説する本が出てきて欲しいですね。
野球にサッカー、水泳などさまざまなスポーツの動作解説から、 自分のランニングにもヒントが欲しいという方に、 ぜひおすすめしたい一冊です。
さっそく、ポイントをチェックしていきましょう。
▼本書より
体の一点に対して、なんとかしようという気持ちが強くなるのは、その気持ちのままでやってもうまくいかないというサインだと私は思います。こだわるから、力んだり、全体のバランスが崩れたりして、結局ほかの欠点が生じてしまいうまくいかない。
優秀なコーチや選手は、例えば肘の位置を修正するのでも、いくつかの引き出しを持っています。
怪我につながる「怪しさ」を持っている人が怪我をする(=怪我の原因は自分である)
現代人は、学校でも社会でも、日常生活の体使いについて教育を受ける機会がほとんどありません。体の姿勢は無意識で生じるもので、そうしようとしているのではなくそうなってしまうのです。
「肩凝りは胸凝り」両腕を前に伸ばして胸を閉じるストレッチをしてみてください。胸を閉じると、僧帽筋が引っ張られ、肩と背中がストレッチされます。逆に背中を閉じると(左右の肩甲骨を寄せると)大胸筋が引っ張られます。
大胸筋も鎖骨に付着しているので、腕を挙げたときに大胸筋に緊張が入ると、鎖骨は後方移動せずに前方移動して閉じてしまいます。上腕も内旋したまま引き挙げられてしまうので、肩甲骨は上方回旋してしまい、肩関節の安定をキープできません。
前肩が普段の姿勢になっている人は、猫背の人が多いと思います。胸と背中の力のバランスがとれるように、胸の筋肉を伸ばし、背中の筋肉の力を強化しましょう。
怪我をしないコンディショニングには、大胸筋のストレッチと、肩のニュートラルポジションの姿勢作りが不可欠です。
両手を挙げる欠伸は、胸をストレッチする運動です。伸びが欠けているので、伸びをするということです。
胸を開くのは歓喜を表します。人は、落ち込んだときには胸を閉じます。姿勢の変化は感情の変化です。
顎には、鎖骨をゆるめる作用だけでなく、運動の方向を指し示し、その方向たな体重移動をするときの推進役を担う作用もあるものと思われます。
後ろ足は外を向いて、前に踏み出す足はまっすぐ前に向けて押す方向の舵取りをする。これが、体の構造(股関節の構造)に沿った自然な体使いです。地面をとらえて体を前に押し出す支持足はわずかに外を向いているのが自然です。
ウサイン・ボルト選手の支持脚の向きを見てください。膝頭と足先が外を向いています。まっすぐ前を向くのは空中にある足(遊脚)のほうです。空中にある足の膝頭は進行方向やや内側を向くのが自然です。
パフォーマンスが高く怪我をしない押し方や歩き方、そして走り方は、力感がない(少ない)動作です。
体全体の重心点は、立位姿勢の場合、体幹のおへそあたりにあります。かかとやつま先にあるのは、重心点ではなく、支持点(荷重点)です。静止して立っているときには、重心点の真下に支持点があるので、踵の真上に重心がある場合は踵重心と言い、つま先の真上に重心がある場合はつま先重心と通常は言われています。
体が前に進むか、後ろに進むかは、重心点と支持点の前後のずれ、つまり静的安定の崩れによって決まるのです。
僕が選手個人の動作や体使いのことに興味を持つと、選手自身もトレーニングや体使いに関心を持ってくれるように感じています。そうすれば、おのずとトレーニングも個別性を大事にしたものになります。
今までは言われることだけをやっていた選手が、自分で本を買って勉強するようになったり、コーチや人に聞くようになったりすることがあって、こういうときに、選手は成長します。
怪我が起こる原因は大きく三つあります。
1.運動量が多すぎる(疲労)
2.過去の受賞歴
3.年齢、体組成
日程が過酷すぎるため回復が間に合わず、筋力低下や筋拘縮が起こり、怪我が起こりやすくなります。調子の良いときに怪我が起こりやすいと言われるのも、試合に出続け、出塁も増え、運動量が増えることが一因と考えられます。
【意識をしてはダメ?ランニング中の姿勢や腕振り】
『トップアスリートに伝授した怪我をしない体と心の使いかた』小田伸午・小山田良治・本屋敷俊介・共著 Vol.117