【ダイエット、減量をやめればパフォーマンスが上がる?】
『一流のコンディション』トレイシー・マン・著 佐伯葉子・訳 Vol.141
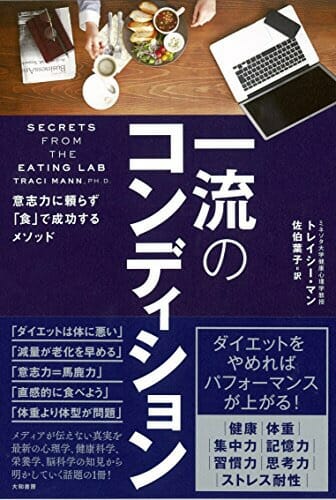
集中力、記憶力、思考力、ストレス耐性…ダイエットをやめればパフォーマンスが上がる?
科学的研究論文を参考に書かれたダイエット本は多く出版されていますが、本日の一冊は、ミネソタ大学の健康心理学の教授で自身の健康と食の研究室で、世のダイエット情報を試し、人々の食習慣を研究してきた著者が、人はなぜ太るのか?(痩せないのか?)について理由を説いた一冊。
食事内容に関する指南ではなく、心理学や脳科学に基づいた、習慣づくりが主な内容となっています。
著者によると、<体重変動の70%が遺伝子によるもの>だそうです。
人は<メニューにカロリー表示をしても、人の行動には何の影響も与えない>や<人は健康によくない行動を起こしたあとには自分の行動を正当化する行動をとる(不健康を正当化する)>など実に興味深いです。
身近で重いたあるのは、お酒を飲み、中華や焼き肉を食べたあとにウコンや健康トクホ飲料を飲む、心当たりのある皆さまもいることでしょう。
<運動は体重が減っても減らなくても健康にいい><本当に大切なのは、自分の体を尊重し、感謝し、それなりに満足すること>というのが著者の主張。
<知り合いに運動着を着たまま寝て、朝一番で運動するという人がいる>という説を読んで、「僕のことだ!」と思いました。昔東京で住んでいた家はロフトで、真冬はランニング練習をついついサボってしまいがちで、そこで考えた習慣が<寝る前にランニング姿のまま寝て、朝は布団を両足で階下へ跳ね飛ばして起きる>でした。これが効果てきめんで、布団がなければ寒くて二度寝もできず、はしごで下へと降りていくうちに目も覚めて、朝のランニング練習を継続することができました。
つい間食をしてしまう。
お菓子がやめられない。
昼食はいつも揚げ物で、ご飯を大盛りにしてしまう。
夕食はお酒を飲み、お腹いっぱい食べてしまう。
帰宅途中にコンビニやベーカリーがあり、つい立ち寄ってしまう。
健康やパフォーマンスに悪影響を及ぼす習慣のある方は、ぜひこの機会に習慣を見直してみましょう。
最近の食事本ブームで、食べものに関する禁止ルールにばかり囚われて、食べものをしっかり味わうということを忘れていたなあ、と思い起こさせてくれました。
ダイエットや食に関する人の心理や行動を描いた本、心理学がお好きな方にはおすすめできる一冊です。
▼本書より
ダイエットにおいてもっとも重要なのは、落とした体重を維持することであり、単に体重を落とすこと自体ではない。
研究では、ダイエット終了後4~5年で、およそ半数の人たちが、ダイエット開始時よりも体重が増えていることがわかった。
体重変動の70%が遺伝子によるもの。
遺伝子が定めた以上、あるいは一定の体重を維持することが難しいこと。それから、体重の増減さえ遺伝子が決めているということが証明された。
ある睡眠研究では、1日5時間しか睡眠を取ることができなかった被験者たちは、5日で約0.9キロ体重が増加したのに対して、1日9時間睡眠を取ったときは、5日間、問題なく体重を維持することができた。
睡眠が不足すると、脳は、たとえお腹が空いていなくても、空腹時と似た反応を示す。
ある食べものをどう認識するかで、人の反応は変わる。
名前が変われば、料理に対する思いも変わり、思いが変われば認識も変わり、食べたあとの感想まで変わる。
2010年以降、アメリカでは20店舗以上あるチェーンレストランは、メニューにカロリー表記することが法律によって義務づけられている。メニューのカロリー表示は、人々の注文内容にほんのわずか、あるいはまったく影響を及ぼさないことがいくつもの研究により立証されてしまった。どの客も、表示には気づいていたにもかかわらずだ。
ある実験で、スーパーの客に「健康によい」シリアルバーと「おいしい」シリアルバーを配ったところ、健康によいと言われた客は、おいしいと言われた客に比べ、食べたあとにも空腹を感じていたことがわかった。
「健康によい」と表現したからといって、より多くの人がりんごを選ぶことはなかったが、心臓によいマークでは効果があった。
健康によい食べものは「健康によい」以外なら、ほぼどんなラべルでも「健康によい」と書いてあるより選ばれる確率が高くなる。
健康的な食べものを食べさせたければ、本人がそれを健康によい食べものだと知っていても、あえて「健康によい」とは表示しないこと。
参加者に、サブウェイの健康的なサンドイッチが、マクドナルドのビッグマックを与え、残りの食事をメニューから自分で選ばせた。すると、健康的なサンドイッチを与えられていた参加者たちは、飲みものにダイエット飲料を選ぶことをせず、多くがデザートを注文した。このような現象をハロー効果と呼ぶ。
無意識に行動できるようになるための方法の一つが、それを習慣にしてしまうこと。
ほとんどの人が、車に乗ると反射的にシートベルトをつける。シートベルト着用は健全な習慣だ。同じ方法を使って、食に関する健全な習慣を作ることができる。
実行意図なら何でもいいということではない。できるだけ具体的なほうが効果的であることがわかっている。
フランス人は、とにかく食べものをよく味わうことで知られる。アメリカ人たちは「これによって体にどういう影響があるのか」ということばかりに気を取られ、あまり食べる楽しみについては考えない。
収入に関係なく、少しでもお金のことを考えるだけで、チョコレートを味わったり、楽しんだりしなくなることもわかった。
肥満者の給料は仕事内容が同じ非肥満者の給料より低いことが複数の研究によって判明した。あるアンケートでは、一番太っている女性参加者は一番痩せている女性参加者より、年収が年間約2万9000ドルも少ないことがわかった。
研究者たちは、体重が減ることばかりに夢中で、「運動は体重が減っても減らなくても健康にいい」という事実を、十分に評価できていなかった。
【ダイエット、減量をやめればパフォーマンスが上がる?】
『一流のコンディション』トレイシー・マン・著 佐伯葉子・訳 Vol.141