【ランナーの復習書として必読】
『走りのサイエンス』桜井智野風・著
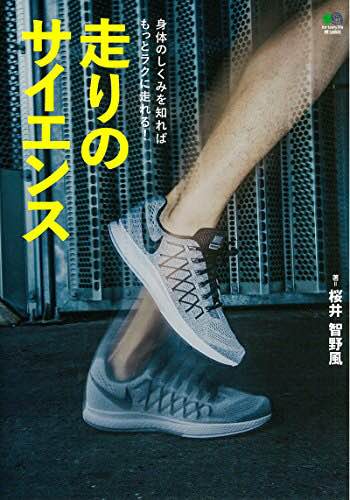 最近、ランニング書籍の出版が増えています。
最近、ランニング書籍の出版が増えています。
日ごろ教えている自分自身ももっと走りについて深く学び たいと思い、国内外のランニング関連の書籍や ノウハウに目を通したり、セミナーを受講することになります。
本日ご紹介する一冊は、『走りのサイエンス』。本のタイトルはガチガチで手に取りにくいかもしれませんが、実に読みやすい一冊です。
読めばなるほど、「「歩く」と「走る」運動のメカニズムの違いは?」といった 走りの基本的なことから、100メートルの世界新記録はどこまで伸びるのかといった 話まで、ランナーとして有益な情報がバンバン出てきます。
一般常識。ことスポーツにおいてはその常識は年月とともに変わっていくことも多いのですが、まずはその常識を知らなければ、トレーニングの効果を発揮できません。
たとえば、僕の周囲では、「100kmウルトラマラソンのような超長距離を走るときには腕をあまり振らないようにしているんです。」といった人の声をたまに耳にします。果たして、この「腕をあまり振らない方がエネルギー効率がいい」という考え方は正しいのでしょうか?
日ごろランニングクラブの仲間と、インターバル走に取り組まれている方で、「インターバル走をするのはスタミナをつけるため」 と考えてトレーニングされている方がいましたら、それは間違いです。間違った効果を期待して、トレーニングをしていることの多さについても、本書で述べられています。
まさにと思ったところは、「「歩き」は人間が生まれながらにもっている"才能"ですが、「走り」を上達させるには"努力"が必要」。
「都会の人は走り出すぎりぎりのところで歩いている」という話が面白かったです。
早速、本書のエッセンスを見てみましょう。
▼ここから
エネルギー効率的には「走る」は「歩く」よりも"無駄"が多い行為。
走ることによって脚が地面を押す力(地面から押し返される力)は大きくなります。すると身体がその力に耐えるために、肩と腰のバラバラな回転を止め、一緒に動くことで無駄を減らすようになるのです。
42.195kmを走った場合を考えると[180×42,195=7,595,100(kg)]となり、約7,600tもの衝撃に耐えていることになります。ランニングスピードを上げると、この値をさらに3.5~4倍近く上昇します。
ランニング中に足が地面に設置する際にかかる衝撃に、一番に対応してくれるのが「腱」なのです。
最近のランニングシューズの衝撃吸収能力があまりにも向上したために、人間の足に本来備わっている足首の底屈という衝撃吸収機能を使う必要がなくなってしまった。
一般成人男性では、体内に貯蔵されているグリーコーゲンは筋肉内に約1500kcal、肝臓に500kcalとされています。しかし、この量は3時間程度のランニングで枯渇することになります。
最近の子供たちの50m走のタイムが、30年前の子供たちと比べても変化がないことが報告されています。平均身長は10%近く伸びており、脚も長くなっていることを考えると、ストライドは伸びているのにピッチが低下している。
長い時間を一定のピッチで走りきるためにはリズムづくりが大切ストライドを維持しながらピッチを上げるためには筋力の増大が必要。
短距離・長距離どちらにおいても、世界レベルに比べて日本のランナーが顕著に劣っているのはストライドである。
脂肪を効率よく使って持久的な能力を向上させるためにも、筋肉に刺激を与えるような筋トレを最初に行うことが必要
グローブやアームウォーマーは、単に寒さで冷えた故障を覆うだけでなく、血流量を減らさないようにすることで、手からの発汗量の減少を防ぎ、運動によって上昇する全身体温を正常に保つ役割も兼ね備えているわけです。
▲ここまで
個人的には、ある意味"歩きのプロ"とも言える、競歩の選手が登山やトレイルランの世界に来たらどうなるのだろうということに関心があります。
「エネルギー効率的には「走る」は「歩く」よりも"無駄"が多い行為」体重の重い人は上り坂でより多くのカロリーを消費するというのは周知の事実ですが、トレイルランに当てはめてみると、体重の重い人は歩きをより多く取り入れた方がよい、という考え方もできますね。
本書で書かれている情報は、多くは既出のものですが、あらためて頭の中を整理するのに良いと思います。 その中で、新しい気づきもあるかもしれません。
走りのメカニズムについての書籍をまだ読んだことがないという方は、ぜひ読んでみてください。
【ランナーの復習書として必読】
『走りのサイエンス』桜井智野風・著